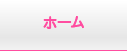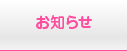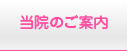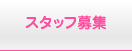2016年3月の記事一覧
-
ハリーのこわいこわい・・・
こんにちは、花粉症がつらい看護師の大澤です☆
いつもハリーの好きなことや好きなものを書いてきたと思いますので、
今回は嫌いなものをご紹介しようと思います ̄∀ ̄①まずこのブログでもよくお話する『シャンプー』
普段は呼ばれると喜んで来ますがシャンプーされると気付くと呼んでも来ません!笑
受付のイスの下や診察室に隠れてバレないと思ってるところが可愛いです^^②ダンボール
これは私が原因で嫌いになった可能性が高いです…
アジリティー感覚でダンボールをくぐらせようと思って近づいたら怖かったようで
今はすごく逃げます゜Д゜③受付の置き物

これも何かが怖いみたいで置いてあるだけなら全然問題ないのですが
持って近づくと走って逃げて、少しの間受付・待合い室に近づかなくなってしまいます笑以上ハリーが嫌いなものたちでした☆
今回も最後まで読んで頂きありがとうございました*_ _)゛ -
花粉知らずのハリー君
こんにちは、看護師の石黒です。
花粉シーズン到来!!という感じで
毎日鼻や目が痒くてつらいですね・・・。
でもハリー君は花粉知らずで、いつもどおり
のんびり過ごしております♪

カメラを向けるとコテッと寝て、

こんな上目づかいや

カメラをくんくん嗅いでみたり

うっとりしたカメラ目線をしてくれました♪

背中に寝癖がついてても知らんぷり!!!
花粉知らずのハリーくんなのでした♪

テヘッ☆2016年03月18日(金) 投稿者 ishiguro | できごと, ハリー君日記, 立川市マミー動物病院ブログ