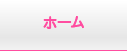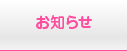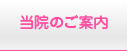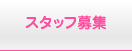2009年10月の記事一覧
-
病院前の花を植え替えました
本日10月28日水曜日は休診日で、午前中私の実家がある武蔵村山市から母が遊びにきてくれました。武蔵村山市から立川市にくるとなるとすごく時間がかかりそうですが、当院は武蔵村山市と立川市とのちょうど境界にあるため、車を使えば10分くらいで実家と行き来が出来ます。そのためいざという時は母が来てくれてとても助かっています。
当院の入り口には開業時から先輩や同僚にいただいたサフィニアなどを飾っていました。私は今まで花を育てたことがほとんどなかったのですが、だんだんと花をいじるのが楽しくなってきて、あっという間に病院の前は花だらけになりました。しかし秋になってそれらが徐々に枯れてしまったため、花に詳しい母に手伝ってもらって冬から春にかけて咲く花に植え替える事にしました。
お昼を昭島市のレストランで食べた後、同じく昭島市のカインズホームに行って花と土を買ってまいりました。たくさんの花があり、どれにしようか母と二人で悩みましたが、かわいらしいパンジーとガーデンシクラメンを購入し、植え替えました。きれいに咲いてくれるのが今から待ち遠しいです。
-
新しい超音波診断装置を導入致しました
10MHzに対応できるプローブを使用したカラードップラー超音波診断装置アロカSSD3500を導入致しました。
超音波診断の精度がこれまでの物より大幅にあがり、より的確な画像診断を行えるようになりました。
マミー動物病院はこれからも病院内設備、医療機器の充実に努めます。 -
スタッフが増えました
9月から動物看護士の大澤希美さんが加わりました。
今日は、大澤さんから皆様にご挨拶させていただきます。「初めまして。9月から動物看護士として働かせていただくことになりました、大澤と申します。神奈川県相模原市から車で八王子市→日野市→昭島市→立川市を通って、通勤しております。まだ慣れないこともありますが飼い主様やわんちゃん・ねこちゃんに信頼していただけるよう一生懸命頑張りますのでよろしくお願いします。」
動物看護師 大澤